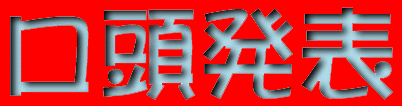
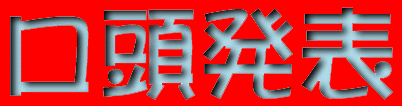
発表番号 |
発表題目 |
所属機関 |
発表者氏名 |
発表要約 |
| O-01 | 福井大学技術部日常・専門研修について | 福井大学技術部 | 橋谷茂雄 | 福井大学技術部の概要と技術部日常・専門研修の発足から今日に至るまでの経過、実施状況などを報告する。 |
| O-02 | 名古屋工業大学における学内技術職員研修報告 | 名古屋工業大学材料工学班 | ○玉岡悟司・安形保則・尾澤敏行・服部博文・森口幸久・山本かおり | 技術職員研修は技術の修得や交流をはかるという目的で行われている。しかし実習については、必ずしも専門でない人も受講するなど、多少問題も生じている。今回は、従来型の研修とは異なった観点から学内研修を企画したので、それについて報告する。 |
| O-03 | 解体新書的に見る廃棄機器の再装置化に関する一試行 第1報 複写定着器をモデルとした廃プラスチックの融着選別装置の試作 | 東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻 | 岩田正孝 | 廃棄プラスチックの再資源化では、樹脂を如何に効率よく選別するかにある。本報では、樹脂の融着温度差を利用する事により高効率の選択選別機構の開発を行ったものであり、研究成果と共に概説する。 |
| O-04 | 電子顕微鏡用試料蒸着装置の改良 | 東京大学大学院理学系研究科・理学部 | 立川 統 | 従来のオイル拡散ポンプによる蒸着装置は始動から終了まで長い時間がかかっていた。また、RPのみによる蒸着装置では分析結果が不安定で実用にならなかった。今回、ターボ分子ポンプを搭載した蒸着装置を開発したので、その結果について報告する。 |
| O-05 | 真空蒸着装置により作製した金属薄膜の膜厚測定および電子顕微鏡観察 | 大阪大学工学研究科 マテリアル科学専攻 | 川村良雄 | 真空蒸着法によりFe、Fe/Cu薄膜を室温でNaCl基板上に作製した。Fe膜厚は触針法、Cu膜厚はICPを用いて測定した。得られた薄膜を透過電子顕微鏡、および電子線回折により調べた。Fe薄膜は多結晶であり、格子定数は膜厚依存性があることがわかった。 |
| O-06 | カルボキシル基を有するクラウノファンの合成と性質 | 群馬大学工学部 | ○猪熊精一・ 西村 淳 | クラウノファンの芳香環にカルボキシル基およびエトキシカルボニル基を導入した化合物を合成し、それらとアルカリおよびアルカリ土類金属イオンとの錯形成挙動を検討した結果について述べる。 |
| O-07 | カロリーメーターによる反応熱を利用した乳化重合の反応速度解析への試み | 福井大学技術部 | 藤田和美 | 乳化重合反応の重合率測定に沈澱剤を用いる方法が一般的である。温度制御システムとして開発した装置をカロリーメーターして利用し、スチレンの乳化重合反応挙動の解析を行うことが出来るかどうかの検討を行った。 |
| O-08 | 微粉分級機の設計製作 | 群馬大学工学部生物化学工学科 | ○江原幸蔵 | 紛体の乾式分級について装置設計・製作・研究を行ってきた。今回は微粉分級機の設計製作に関して報告する。 |
| O-09 | コールドウエルドによる原子炉照射のためのミニ真空カプセルの製作 | 京都大学原子炉実験所 | ○宮田清美・小高久男 | 照射のためのスペースは狭いので、石英管などで試料を封入する場合には温度上昇が避けられない。そこで試料を昇温させない、コールドウエルドによるアルミニウム管の圧着方法を確立したので報告する。 |
| O-10 | 光電子増倍管の面感度測定装置について | 大阪大学理学研究科 | 〇松岡健次・北見豊吉・杉本章二郎 | 高エネルギー加速器研究機構の高エネルギー研究グループと共同で光電子増倍管の面感度を測定をするために「光電子増倍管真空紫外波長領域感度測定装置」を開発した。本研究会で装置の概要と問題点について述べる。 |
| O-11 | 光ファイバー表面プラズモンセンサ | 静岡大学工学部 | 松井義和 | 最近、化学分野での応用研究が盛んになり始めた表面プラズモンセンサの原理と、今後、発展が期待される光ファイバー表面プラズモンセンサの基礎特性と、各種溶液、LB膜累積結果等について報告する。 |
| O-12 | EPMAによる不均質試料の定量分析技術の開発 | 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 | ○吉田英人・下司信夫 | EPMAの定量分析とマップ分析機能を組み合わせ,析出相のある金属や多数の鉱物からなる岩石などの,多相系からなる不均質試料の平均化学組成を,非破壊で精密に決定する方法を開発したので報告する。 |
| O-13 | 低温SEM-CL装置の開発とダイヤモンド薄膜の光学的機能評価 | 東北大学金属材料研究所機器開発技術コア | 伊藤 学 | ワイドギャップ材料用SEM-CL装置に冷却系を製作し、光検出系の改良を行った。発表では改良の模様及びこの装置を用いて得られたダイヤモンド薄膜の機能評価について報告する。 |
| O-14 | 金属中微量元素定量のための試料前処理法の検討 | 東北大学金属材料研究所技術室 | ○芦野哲也・板垣俊子・坂本冬樹 | 金属試料中の微量元素を定量する際、主成分元素による測定への影響を除去するため測定目的元素の分離・濃縮が必要となる。今回、当セクションで行われている試料前処理法について報告する。 |
| O-15 | インターネットライブ | 大阪大学産業科学研究所技術室 | ○田中高紀・相原千尋・山田 等 | 当研究所では各種国際シンポジウム等をネットワークを利用した「インターネットライブ」を行っている。我々の職務上コンピュータ、ネットワーク等を利用した業務を行っているゆえ関連した業務と考え、今回それを発表する。 |
| O-16 | 高分解能測定による構造解析 | 東北大学大学院理学研究科附属化学機器分析センター | ○佐藤年男・門馬洋行 | 当センターの質量計は、大型のため高分解能測定を精度よく測定できるので、フラグメントピークの高分解能の測定も行っている。その測定・データ処理から組成式を求め、構造解析に用いている。 |
| O-17 | 四重極質量分析計のデータ収集およびその解析の高速化・高精度化 | 鈴鹿工業高等専門学校電子情報工学科 | ○西村吉弘・河野純也・井上昌子・松村 哲 | スパッタ放電ガスの分圧測定を四重極質量分析計(QMS)を用いて、特定のm/e(質量電荷比)を有するイオンを分離し検出を行う。その計測結果を計算機システムとの結合による高精度化・イーサネットを用いた高速度化を図る。 |
| O-18 | W-band ESR(94 GHz 電子スピン共鳴測定装置)の紹介 | 岡崎国立共同研究機構分子科学研究所 | 酒井雅弘 | コマーシャルベースとしては日本で第一号機となるW-band(94GHz) 電子スピン共鳴測定装置がにBruker社より納入された。講演では、他の周波数のESRとの違いなど装置の仕様・性能およびデータを紹介する。 |
| O-19 | 超伝導NMR分光計による体積磁化率の測定とその問題点 | 大阪大学有機光工学研究センター | 寺脇義男 | Flathの試料管を用いて超伝導磁石の分光計でスペクトルを測定すると内管の円筒型部分と球形部分の試料は分かれてシグナルを与える。これらのシグナルを利用して体積磁化率を求める方法とその問題点などについて述べる。 |
| O-20 | 学内専門研修におけるNMR測定技術の修得 | 福井大学技術部 | ○森田俊夫・下村与治・漆崎美智遠 | 発表では、有機化学の分野に携わる者として化合物の構造解析等に必要な知識を得るため、機器分析センターに設置されているNMR装置(液体用 LA500型)を利用し、学内専門研修を通して修得した特殊な測定技術・解析方法および その研修内容について述べる。 |
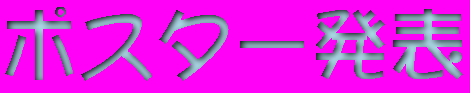
発表番号 |
発表題目 |
所属機関 |
発表者氏名 |
発表要約 |
| P-01 | セッション記号および講演番号表示機能を有する研究発表会用タイマー装置の製作 | 福井大学技術部 | 酒井孝則 | 当日使用させていただく研究発表会のためのタイマー装置を製作したので紹介します。頭発表会場においてセッション記号と講演番号並びに発表経過時間を常時電光表示し、自動的に予鈴、発表終了鈴などを報知する装置です。 |
| P-02 | 循環型冷却機の製作 | 東北大学科学計測研究所技術室 | 千葉 寿 | 近年、当研究所において大々的に推進されている省エネルギー対策の一環として実験装置の冷却水を循環型へ移行する動きが活発になっている。今回試作した冷却機では低価格で水の使用量を約200分の1まで削減することに成功した |
| P-03 | 学科内LANと学科のパソコン環境 | 群馬大学工学部生物化学工学科 | ○江原幸蔵・齋藤和子・伊田尚子・藤生明美・柳原美智子 | 学科LAN委員会の活動・学科共通コンピュータ室の管理と授業への利用形態及ぴ学科のパソコン環境について報告する。 |
| P-04 | 有限要素法解析ソフト「ANSYS」を用いた振動解析の実例 | 東京工業大学精密工学研究所 | 高橋久徳 | 実験を行う前に、ANSYSを用いて振動解析、圧電解析を行っている。この作業を行うことによって理論値と実験値の比較をすることが出来る。また最適な設計方法を導き出すことも可能である。 |
| P-05 | 断面観察用薄膜試料作成法 私の場合(1) | 大阪大學産業科学研究所技術室 | 石橋 武 | 透過型電子顕微鏡を用いて半導体積層膜などを高分解能観察するのに必要不可欠な技術の1つに断面試料作成法がある。平成11年度の技術研究会でも東北大科研の佐藤二美氏が詳細にその作成法を発表されていた。その後、私も断面試料作成の必要に迫られ悪戦苦闘したが、今回はそれらの経験をふまえ具体的な作成方法を報告する。 |
| P-06 | γ-Feを内包するカーボンナノカプセルの作製の試み | 三重大学工学部 | ○前田浩二・中川浩希・和藤 浩・中村昇二 | 現在までにバルク,薄膜,微粒子等いずれの形であれ,γ-Feの合成がほとんど研究されていないことから,アーク放電による凝縮法により,γ-Fe微粒子内包カーボンナノカプセルの合成を試み,その分析を行った. |
| P-07 | 銅の酸素分析用標準試料の試作と低濃度域分析精度の検討 | 名古屋大学工学研究科材料系技術センター | ○高井章治・栗本和也・山田真志 | 酸素濃度を制御し,かつ分析値のばらつきが少ない銅の酸素分析用標準試料の作製を試み,それに伴い低濃度域(5~10ppm程度)の微量分析の精度についても検討した。 |
| P-08 | 原子吸光分析法による生体微量元素の測定 | 富山医科薬科大学実験実習機器センター | ○澤谷和子・森腰正弘・野手姫代美 | 私達は食物を通じて体内に微量の金属元素(Fe,Zn,Al,Ca等)を取り入れているが、これらの体内蓄積濃度の変動と健康障害との関連について、血液透析者の血清を用いて検討した。 |
| P-09 | 免疫組織化学における抗原性賦活化の工夫(各ステップにおけるマイクロウェーブ照射法の有用性) | 富山医科薬科大学教務部研究協力課技術室 | ○熊田時正・八田秀樹 | 免疫組織化学過程の全般(内因性ペルオキシダーゼブロック、一次・二次抗原抗体反応、及びDAB発色反応)におけるマイクロウェーブ照射法が抗原性の検出感度並びに、反応強度の向上に有効であった。 |
| P-10 | 塩素系誘導結合型プラズマ(ICP)エッチングにおける発光分光分析 | 東京工業大学精密工学研究所 | 松谷晃宏 | 半導体レーザの高性能化には素子構造をミクロンサイズに微細加工する必要がある。半導体レーザの材料として重要なInPの垂直平滑ドライエッチング技術は、 |
| P-11 | 光磁気記録膜の磁区観察法 | 名古屋大学工学部 | 熊沢正幸 | 光磁気記録膜は、MO・MDディスクに実用化され、さらなる高密度化の研究が行われている、シミレーション等の検討のため記録状態の観察は重要視されている、本発表では、磁区観測用試料の作成・MFM観察・ローレンツ顕微鏡の観察例について報告する |
| P-12 | 質量分析計冷却水循環装置のトラブルとその対策 | 名古屋工業大学応用化学科 | ○山本かおり・川井正雄 | 昨年度から,質量分析装置の管理運転に関わるようになった.この一年間に起こった様々なトラブルのうち,今回は主として,冷却水循環装置のメンテナンス不良のために起こってしまったトラブルについて報告する. |
| P-13 | フルオロカーボンフィルムの分析 | 名古屋大学工学部 | 高田昇冶 | ドライプロセスに用いられるフルオロカーボンプラズマでは、真空容器壁等に絶縁膜を生成する。これまで、この膜の分析を、CI-MS、SEM等を用いて行ってきた。今回、これらの分析手法の問題点などについて報告する。 |
| P-14 | 質量分析の精密質量測定(FAB)に於ける標準試料の検討 | 千葉大学分析センター | ◯原 律子(千葉大学分析センター)坂部千賀子(北里大学薬学部共有機器室) | 質量分析の高分解能測定(FAB)では標準試料として平均分子量の異なる各種ポリエチレングリコール(PEG)が一般に単体で使用されている。筆者は各種PEGを混合した標準試料を作成し検討したので報告する。 |
| P-15 | 二重収束質量分析計におけるFAB法高分解能測定の報告 | 北里大学薬学部共有機器室 | 北里大学薬学部共有機器室 ○坂部千賀子 千葉大学分析センター 原 律子 神奈川県警察科学捜査研究所 阪柳正隆 北里大学薬学部共有機器室 中川暁子 |
二重収束質量分析計(中型、加速3Kv)で分子量 700 以上の化合物も、FAB法高分解能測定を日常的に精度良く行っているので、大型質量分析計(加速10Kv)の比較も交えてその測定結果を報告する。 |
| P-16 | EPMA分析による一考察 | 熊本大学工学部附属工学研究機器センター | 宇藤倢堅 | 日常のEPMA依頼分析業務に於ける疑問点を考察する。 |
| P-17 | 色素-金属イオン錯体のNMR測定技術 | 福井大学技術部 | 下村与治 | 窒素を配位原子とした配位子と金属イオンとの錯体をNMR測定法により評価する。特にアルカリ金属イオンとは錯安定性が低く、溶媒中の水など周りの環境により結合の解離が懸念される。よって測定の前段階である試料調整について主に検討したので報告する。 |
| P-18 | 教員養成過程(理科系)学生の基礎教育へのNMR導入 | 和歌山大学教育学部 | 中村文子 | 理科系全般の教員にとって、物質の性質を示す最小単位の分子の構造及び運動についての理解は不可欠です。この目的のために、基礎教育における化学実験授業にNMR測定装置を導入することを提案します。 |
| P-19 | 物理化学学生実験における分光学的実験例 | 群馬大学工学部応用化学科 | ○海老原啓子・田口二三枝 | 物理化学学生実験(3年)テーマにおける芳香族化合物の紫外可視吸収スペクトルによる構造変化の検討および、けい光測定による励起分子の緩和過程、消光実験の例を紹介する。 |
| P-20 | 学生実験に関する開発工夫と技術職員の諸活動 | 大阪市立大学基礎教育実験棟化学実験室 | 阿武美智子 | 学生実験(全学基礎教育、年間350~500人対象)に携わる技術職員としての学生実験の中での改良点、工夫などをまとめてみたい。 |